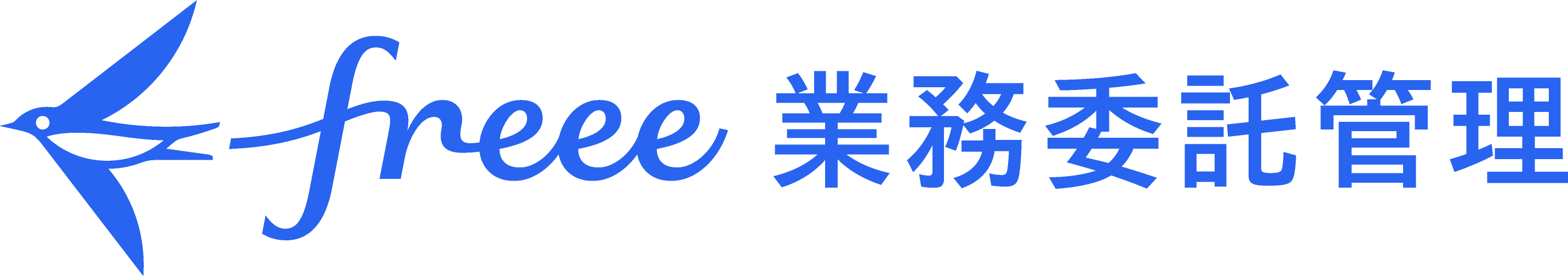下請法の対策マニュアル!ガイドラインを遵守してリスク回避を図る

下請法は、製造委託、修理委託、情報作成物制作委託、役務提供委託の4種類に適用されます。多くの業務委託が対象となると考えましょう。下請法対策をすべて網羅したマニュアルを作成するのは困難ですが、公正取引委員会が定める運用基準や、各省庁によるガイドラインなどに個別の業種に応じた違反事例・改善事例が記載されていますので、これらを参照して下請法対策を行いましょう。

CONTENTS
■マニュアルは作成できる?全業種で活用すべき、公正取引委員会の講習会テキストや各種パンフレット
下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」)違反を未然に防ぐには、下請法のマニュアルを整えることが望ましいですが、全ての内容を自社で作成することは困難です。
下請法マニュアルについて、以下のとおり説明します。
・自社でマニュアルは作成できる?
・活用したい、公正取引委員会の講習会テキスト | 下請取引適正化推進講習会
・理解を深めるために有効な下請取引適正化推進講習会と動画
・知っておきたい、公正取引委員会の各種パンフレット
順を追って見ていきます。
●自社でマニュアルは作成できる?
親事業者は、違法意識なく下請法違反をするケースも多くあり、法令順守の観点から下請法のマニュアルを整備したいと考える企業も多いでしょう。
しかし、下請法の全てを自社だけでマニュアルに網羅することは困難です。加えて、下請法の改定や運用基準、ガイドラインの変更があるたびに、マニュアルを更新することは非現実的と考えられます。更新されていないことが起因して、下請法違反となるような事態は避けるべきです。
コンプライアンスの観点から、自社におけるマニュアル作成は最低限とし、信頼性の高い公正取引委員会や各省庁で発行されている刊行物を活用することがおすすめです。
●活用したい、公正取引委員会の講習会テキスト | 下請取引適正化推進講習会
公正取引委員会は、下請取引の適正化に向けて、毎年11月を「下請取引適正推進月間」とし、この期間に下請法対応の啓蒙を集中的に行っています。この取り組みの一環として、下請取引適正化推進講習会を開催しており、この下請取引適正化推進講習会テキスト(以下、「講習会テキスト」)を公正取引委員会のサイトで毎年公開しています。
この講習会テキストは、下請法の内容や親事業者における義務や禁止事項、下請法違反の未然防止の取り組みのほか、下請法の運用状況や調査内容、法律や運用基準などの各種改正などを詳細に解説しています。
(参考)公正取引委員会:「各種パンフレット(下請法 講習会テキスト)」
●理解を深めるために有効な下請取引適正化推進講習会と動画
講習会テキストは、公正取引委員会のサイトで公開されており、誰でも閲覧可能です。しかし、情報量は数百ページにわたるため、個人がテキストを見るだけで網羅的に理解するのは困難でしょう。
公正取引委員会では、講習会テキストを用いた「講習会動画」を公開しているほか、オンデマンドで参加できる「オンライン講習会」も開催しています。ただし、オンライン講習会は、接続できる人数に限りがありますので、早めに申し込みをする必要があります。
また、公正取引委員会では、下請法の内容や知っておきたい取引のルールなどを分かりやすくした動画を YouTube の「公正取引委員会チャンネル」で公開しています。社内のコンプライアンス研修などに活用してみてください。
(参考)公正取引委員会:「下請法・優越的地位の濫用規制に関する講習会」
(参考)公正取引委員会:「公正取引委員会チャンネル – YouTube」
●知っておきたい、公正取引委員会の各種パンフレット
公正取引委員会は、講習会テキストのほかにも、下請法に関するガイドブックや各種パンフレットを公開しています。親事業者向けのポイントや下請事業者向けの知っておきたい下請法のポイント解説のほか、下請法の各種リーフレット、ガイドブックを掲載しており、下請法に関する知りたい重要情報が満載です。
親事業者向けのガイドブック「ポイント解説下請法」では、下請法の対象取引を図解しているほか、親事業者の義務や禁止事項を事例や注意点を上げて説明するなど、わかりやすくまとめられています。
コンテンツ業界を対象とした「コンテンツ取引と下請法」では、親事業者の義務であるコンテンツ作成依頼時の書面交付について、発注サンプルを例示するなど実務に即したガイドブックとなっています。ぜひ、参考にしてください。
(参考)公正取引委員会:「各種パンフレット」
■必見!業種ごとに示された各省庁のガイドライン
下請法違反を未然に防ぐには、ここまで説明してきた公正取引委員会の講習会テキストや各種ガイドブックで理解を深めることが役立ちます。しかし、業界特有の取引などに応じた各種事例などは、網羅できません。
ここでは、各省庁が発行する業界ごとに示された下請適正取引等の推進のためのガイドライン(以下、「ガイドライン」)は、以下のとおりです。
・ガイドラインが整備されている対象業種
・ガイドラインは過去の事例が記載されていて参考になる
順を追って説明します。
●ガイドラインが整備されている対象業種
ガイドラインは、下請事業者と親事業者との間における下請取引の適正化を目的に、国が策定しています。業種に応じたベストプラクティス(望ましい取引事例)や問題となり得る取引事例等が分かりやすく示されていますので、実務的な内容を把握することが可能です。
経済産業省、総務省など、各業種を管轄する省庁が策定し、2021年12月末時点で下記19業種のガイドラインが発行されています。
1.素形材
2.自動車
3.産業機械・航空機等
4.繊維
5.情報通信機器
6.情報サービス・ソフトウェア
7.広告
8.建設業
9.建材・住宅設備産業
10.トラック運送業
11.放送コンテンツ
12.金属
13.化学
14.紙・加工品
15.印刷
16.アニメーション制作業
17.食品製造業
18.水産物・水産加工品
19.養殖業
(参考)中小企業庁:「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」
●ガイドラインは過去の事例が記載されていて参考になる
ガイドラインは、業界における過去の事例や注意点とともに、改善事例やベストプラクティスを示しています。業種に即した具体的な内容になっており、マニュアルとしても十分に活用できるものとなっています。
ガイドラインに示されるベストプラクティスは、下請法の遵守状況等について、業界内の対象企業に調査の上で改善事例をまとめたものです。下請法違反になり得る事例も具体的に示されていますので、ぜひ、参考にしてください。
■下請法違反行為があると公正取引委員会から勧告・調査を受ける
下請法違反が発覚すると、公正取引委員会から勧告と公表がなされ、企業評価が低下するおそれがあります。場合によっては課徴金や罰則の対象ともなりえます。
ここでは、下請法違反があった場合のリスクについて説明します。
・公正取引委員会は下請法違反に対して調査、勧告を行える
・公正取引委員会からの調査、勧告を回避するにはガイドラインを遵守することが重要
順を追って解説します。
●公正取引委員会は下請法違反に対して調査、勧告を行える
公正取引委員会は、下請法違反の未然防止を目的に、下請法に基づく定期的な書面調査や立入調査のほか、相談センターなどにおける監視体制を整備しています。
この監視体制の下、親事業者における受領拒否や買いたたきなどの下請法違反が発覚した場合は、次のような流れで処理されます。
・親事業者に対する調査・検査
・勧告(公表)、指導
・親事業者による改善報告書の提出(勧告に従わないときは排除措置・課徴金納付命令)
公正取引委員会は、下請法違反に対し、不利益な取扱いや遅延利息の支払いなど、必要な措置を勧告・指導し、親事業者に改善報告書の提出を求めます。親事業者が勧告に従わないときは、排除措置命令、課徴金納付命令がなされることがあります。また、下請法3条、5条(下請代金支払遅延等防止法)に違反に該当した場合は、親事業者である会社と違反した行為者に、最高50万円の罰則が課される可能性があります。
●公正取引委員会からの調査、勧告を回避するにはガイドラインを遵守することが重要
下請法違反について勧告を受けた場合、公正取引委員会のサイト「下請法勧告一覧」において企業名が公表されます。ただし、親事業者が自発的に下請法違反行為を申し出た場合、公正取引委員会は、一定条件の下、勧告を行わないとされています。
(参考)公正取引委員会:「下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者の取扱いについて」
親事業者は、企業名が公表されると、社会的信用や企業評価低下というリスクが生じます。コンプライアンスの観点から、公正取引委員会からの調査、勧告がなされないよう、ガイドラインを遵守することが重要です。
■最後に
本記事では、下請法対策として、公正取引委員会が公表している講習会テキストやガイドブック・リーフレットを活用するほか、業界に即した内容はガイドラインを活用することが有用であることを解説しました。
下請法は、公正取引委員会が毎年実施する調査などの実態を分析したうえで、運用基準の改定や法改正などが行われるため、定期的に新しい情報を入手して理解を深める必要があります。
毎年11月を「下請取引適正推進月間」として、講習会の実施やテキストの改定も行われます。この時期に合わせて、「講習会を受講する」「ガイドラインを見直す」など、下請法やガイドラインを遵守し、コンプライアンスを徹底しましょう。
(下請法に関わる資料が欲しい方はこちらよりダウンロードいただけます。)
監修者コメント
下請法違反の行為をすると、勧告を受けただけで公表されてしまいます。現代ではネットを通じて簡単に情報が拡散されてしまうので、評判が悪化すると新規取引の獲得や既存の顧客への影響、売上低下なども心配でしょう。現代は中小事業者にもコンプライアンスが求められる時代です。自社でマニュアルを作らなくてもわかりやすく下請法を理解できる公的な情報源が多数あります。必要に応じて参照し、正確で最新の知識を持ちながら対応を進めましょう。
■本記事の監修者
福谷陽子/元弁護士 兼 監修ライター

保有資格:司法試験合格、簿記2級、京大法学部在学中に司法試験に合格。10年にわたる弁護士実務経験とライティングスキルを活かして不動産メディアや法律メディアで精力的に執筆中。不動産については売買、賃貸、契約違反、任意売却、投資、離婚、相続、解体や許認可等、あらゆる分野に精通。